在来工法による家づくりの流れ
1.着工前
地盤調査をしました。この辺は関東ローム層が分厚く堆積しています。結果は良好でした。杭の必要はありません。



基礎の着工に先立ち、梁の加工をします。
作業場に原寸型(薄いベニヤ板)を制作しました。化粧垂木(屋根下地板をつけるための角材)の欠き込位置などを決めます。
垂木を吊る梁もあり、精度が要求されます。


階段の中壁は長い1枚板。これも模型を造りおさまりを確認した上で、あらかじめ欠き込を造っておきます。

地下部分の階段中壁はコンクリートです。型枠に欠き込のための木を付けておきます。
事前の作業がけっこう多いのです。

軒天井の換気穴に虫よけのパンチングメタルを付けておきます。
2.基礎工事
地下室があるため基礎工事は大きく2工程に別れます。地下部分の壁と地上部分のベタ基礎です。


地下室は畳3畳半ですが、余掘りを含めるとなかり大きな穴になります。
コンクリート打設後、養生が終わった段階で防水剤を塗布します(ここは地下水位は低いので水が湧かないとの判断)。



ベタ基礎部分はしっかり割栗石を敷設。鉄筋は構造計算によりしっかりしたものになりました。
外張り断熱のウレタンフォーム(シロアリ対策の防虫剤添加された製品)も一緒に打設します。


コンクリート打ちは朝からします。ベランダの独立基礎も忘れずに!

階段中壁(地下部分)はきれいに打設できていました。
3.上棟

上東に先立ち、垂木の塗装も済ませます。あらかじめ塗っておくことできれいに仕上がります。


現場では上東に先立ち土台敷きをします。大工さんが墨出(土台の芯位置を基礎に記すことで土台を正確に据え付けることが出来ます)して、丁寧に土台を設置します。
また、土台の高さが正確に揃うよう、レベルを見ながら土台の下に薄いパッキンを敷き重ねます。誤差1ミリ以下で正確に据え付けます。

朝から作業開始し、夕方ころ上棟しました。
4.屋根工事
上棟後は屋根工事です。


湾曲した屋根の梁に垂木(屋根の下地板『野地板』を付けるための角材)を付けていきます。垂木は通常、梁の溝に落とし込みます。
この建物は天井高を確保するために1箇所だけ梁から吊り下げます。前もって作業場で原寸型をおこし、正確に吊り材や溝を造っているのでスムース、かつきれいに出来上がりました。

塗装済みの野地板を張り、きれいな湾曲した天井を表現できました。

下地が出来たら断熱材を張ります。
断熱材が浮き上がらないよう、また、気密を保つよう断熱材の上から薄いベニヤ板を張ります。



ベニヤ板の上には通気用の角材を打ち付けます。角材の上に屋根下地の合板を張ることで通気のための空間ができるのです。夏の暑さ、壁や屋根内の除湿に効果を発揮します。
通気層は土台から壁を通り、屋根面までつながっており建物の構造部を健全に保つ役割を果たします。

その後、屋根の防水ルーフィングを張り屋根仕上げをします。
5.TIP工法



この建物はTIP工法という特殊な通気+耐震工法を採用しています。板を斜めに張ることで耐震性を高められるのです。たくさんの筋交いが入っているのと考えてください。
また、斜めに張った板の外側に断熱材を張るので、板の隙間を空気が自由に動きます。断熱材の内側、すなわち内装材と柱や梁の間の空気が自由に動くことができるのです。
浴室、洗面、押入れなどから入った湿気を逃がすことができ、建物の耐久性を高める効果があります。
6.耐震筋かい
耐震筋交いをいれます。


当事務所では在来工法の場合、基本的には筋交いによる耐震壁を採用しています。湿気による被害を合板よりも無垢の筋交いの方が受けにくいからです。
余談ですが、この建物の柱は紀州・山長の70年杉を使っています。ヒノキバージョンもあります。
7.断熱工事


断熱材を設置し、防水テープを貼り通気胴縁を付けます。寝室と居間の間の壁には防音用としてセルロースファイバーを充填します。車通りの多い場所に立つ家にはセルロースファイバー充填断熱を採用することもあります。
(『SE構法による家づくりの流れ』の「12. 断熱工事に先立って」「13. 断熱工事」参照)
8.遮音

2世帯住宅なので、2階床下の排水管は遮音性の高い仕様としています。

また、床下地として遮音シートやセルロースファイバーを充填しています。
9.塗装

外壁杉板の塗装をします。色見本を造ってもらい決めました。


塗装は板の裏にもします。表は2回塗をします。雨水が板の継ぎ目からしみ込まず外側に排水されるよう、継ぎ目は斜めにカットします。もちろん、カットしてから塗装します。
塗装はペンキではなく、色のついた自然系オイルです。
190
10.左官工事


メインの外壁は左官仕上げです。ひび割れ防止のメッシュをすきこみます。
11.床張り

玄関の上がり框が来たということで工務店まで見に行きました。


現場では1枚ずつ丁寧にフローリングを張っていきます。
12.屋上デッキ


自邸ということもあり、屋上やベランダデッキは自分で造りました。
材料の無駄をなくすために数種類ある材料の寸法から丁度よいものを選びました。現場では仕上げ材料の切断はしませんでした。
13.庇

何種類もの庇があります。
屋上デッキ製作の写真にある、出入り口上の湾曲したステンレス1枚板の庇。
玄関庇は杉板張りです。
2階ベランダ庇は、手前は透明で奥は夏の日差しを遮るために穴開きセメント板を貼っています。
14.内装・建具

内装はほとんどが左官仕上げです。
同じ色ですが混ぜものを変え、いろいろな雰囲気を演出しました。

建具や家具は専門の職人さんに造ってもらいます。
工房では小さな収納の小扉を仕上げていました。

完成写真はこちらから
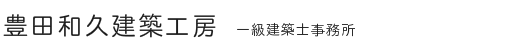
 HOME
HOME