SE構法による家づくりの流れ
1.敷地確認

敷地確認。
12坪ちょっと。
設計には一工夫必要。
2.道路よう壁の基礎位置確認

よう壁の基礎の位置を確認するために試掘。
思ったより小さな基礎。本来は民間の敷地内には無いものですが・・・。
基礎の設計にも一工夫必要。
3.地盤調査

工務店を決めて地盤調査。
当初から設計や見積もりに関与することで、責任を持った見積もりと工事が可能となり建て主さんにも安心感を持ってもらえます。
土質も確認することで、決め細かな設計ができます。
4.根切りと杭工事


根切り開始。
いよいよ道路よう壁の基礎全体が現れました。このよう壁基礎に建物の荷重をかけないような設計をしました。よう壁近くには杭も出来るだけ細かく入れます。
5.基礎工事



杭に引き続き、大事なものが基礎工事です。上が良くても基礎がおろそかでは何もなりません。建物の規模のわりには大袈裟に見える配筋です。
今回は敷地内に道路よう壁の基礎があり、その基礎に建物の荷重をかけない特別な配慮がされています。基礎配筋については、保障の対象にもなるので第三者に検査を依頼します。特に問題ありませんでした。

基礎の立ち上がりの部分(ピンクの○印)に注目です。
鉄筋が切り放しではなく、折り曲げて抜けなくなっています。細部まで配慮し、丈夫な基礎を造ります。
6.型枠工事


配筋が完了したら型枠工事です。
鉄筋の外側には決められた厚さ以上のコンクリ-トが無くては
なりません。被りと言います。被りが十分にとれる様に、また今
回は基礎の高さが90cmあるのでコンクリ-ト厚は20cmです。
また、打ち放しのきれいな表情を造る為にパネコ-ト(ベニヤ板
にウレタン塗装された型枠材)を使用し、きちんと割付してもらい
ました。
2枚目の写真には断熱材が型枠の内側に挟んであります。型枠
を一定の巾に保つための鉄の棒を通すのですが、型枠を一旦組
み、断熱材の穴の位置を合わせ、型枠を解体し、断熱材を挟み、
再度組み立てています。断熱材の穴を出来るだけ小さくするため
の見えない苦労がありました。
要所を測り確認し、いよいよ次はコンクリ-ト打設です。
7.コンクリート打設


コンクリート打設は早朝からはじめます。
ホースで流し込む人、コンクリートを隙間無く詰めるためにバイブレーターを挿入する人、間に入った気泡を抜くために型枠をたたく人・・・。それぞれが息を合わせて作業します。最後に上端を平らにするのですが、精度を上げる為に細心の注意を払います。おかげさまできれいに打ちあがりました。
慌しい暮れの上棟を避けて年明けとしました。年末年始の雨が心配です。
8.上棟待ち

上棟を待っています。
待っている間に水道や排水管を埋設したり、作業場では屋根の部材の原寸を起こして材料を刻んだり、宇都宮の工場では特注のスライド式トップライトの製作を進めています。現場は止まっているようですが、作業は進みます。


一方、上棟したら工事は加速します。外壁の色を決めるべくサンプルの絞込みをしつつ、色彩検討をはじめました。
9.上棟

上棟しました。
年末に上棟の予定でしたが、年末年始の休工中に雨が降るのを嫌うなどの理由もあり少し遅れました。その間、外部配管、屋根下地材の加工、トップライトの製造など他に出来ることを進めていました。これから工事は一気に進みます。
この建物、1階の半分が車庫(耐震壁が無い)、更に建築的には3階建て+小屋裏(ロフト)です。構造計算上は屋根裏の荷重もしっかり見ているので1階、2階の壁が強化されています。SE構法により実現した木造住宅といえます。
10.屋根防水・窓の防水

上棟の後は屋根工事です。
この家には屋上があるので屋上防水をします。防火性のある防水材を塗布します。

今回はトップライトがあります。トップライトの廻りはトラブルが多い箇所なので、大工さん・監督・設計の3者でよく話し合い、設計図とは違うおさまりにしました。結果信頼性は向上したと思います。
現場で実際のものをみて変更し、より良くすることも現場監理の大切なことのひとつです。


防水は窓廻りもします。ル-フィングを使うこともありますが、最近は専用の防水ゴムを使います。ちょっとだけお金がかかりますが、防水はお金に代えられない性能だと考えています。

屋根工事の重要なことのひとつに通気もあります。外壁通気と屋根通気の一体化は建物の耐朽性、快適性の上では大変重要なことです。

補足ですが、この家は防蟻にヒバ油を使っています。内部の左官、床はもちろん自然素材ですが、見えない防蟻にもこだわりました。色つきなので塗った箇所が一目で分かります。
11.断熱・設備工事


内装と平行して設備や断熱工事が進みます。
屋根工事が完了し窓がついたらいよいよ耐震壁を設置しながら内装工事にかかります。この家は防音効果を期待してセルロ-スファイバ-充填断熱
としていますが、天井高を確保するために最上階屋根裏の断熱は発泡樹脂系の断熱材を採用しています。屋根から騒音が聞こえることはありません
からね。
写真銀色に見えるのが発泡樹脂系の断熱材です。浴槽にはハ-フユニットのユニットバスを使います。比較的安価で、壁の仕上げは自由になります。
今回はヒノキとタイルを併用。しかし、この浴槽は断熱をしていません。よって、現場にて発泡ウレタンを吹きつけ、自前の断熱浴槽に仕立てます。
効果はバッチリ!

設備工事も順次進みます。
排水管が部屋の天井を通る際は遮音材で被覆します。細かな配慮がいっぱいの住宅です。
12.断熱工事に先立って


セルロ-スファイバ-充填断熱を採用しています。メリットは断熱性+湿度調整機能+遮音性です。新聞紙を綿状に細かく裁断し麻の繊維を繋ぎとして混入することで、長期間の使用でも沈下すること無く機能を発揮します。そしてなにより100%リサイクルなのでエコです。今回は車通りが多い通りに面しているので採用しました。
断熱に先立ち、外回りの納まりをつけなくてはなりません。サッシを設置し、庇を付け板金工事を完了させます。雨水の浸入を防げるようにすれば断熱工事に進めます。
13.断熱工事



木製の玄関ドア枠や螺旋階段も厄介ですが、これも完了しないと断熱に進めません。最後に残った作業が完了し、断熱工事に進みました。
セルロ-スファイバ-が特殊なシ-トの中にパンパンに詰まっています。セルロ-スファイバ-はホ-スで圧送するのですが、慣れた作業員が充填させることになっています。あとで充填が不十分なところが出ないよう配慮しているそうです。
14.内装と外装


本格的に内装に入っています。
地震の後、建材が入手しにくくなっていますが何とか進めています。床も張り終えました。浴室はヒノキとタイルを張り分けます。水がかかりやすい下の方や、シャワ-ホ-ス周辺にタイルを張ります。
外部はル-フィングを張り、ラス(金網)を打ちつけ左官の下塗りが完了しました。しばらく養生し、仕上げの吹付けです。
15.内外装仕上げ工事


外壁吹き付けが完了。樋などの設置が済んだので足場を撤去しました。建物を覆っていたシ-トが無くなり、建物が姿を現しました。
玄関扉などの塗装が残っていますが、一応姿のお披露目がすんだ感じです。

ベランダのデッキ材も完了しました。耐朽性重視で板の下地はアルミかデッキ材と同じ材料を使います。
雨樋の落とし口は掃除が可能なように取り外し出来るようになっています。


玄関廻りも格好がつきました。扉は下から20cmの部分のステンレスキックプレ-ト(扉の下のほうが傷まないように保護ステンレスを付けます) をつけて塗装をします。今回はベランダ手摺と同じこげ茶です。余談ですが、こげ茶色は床のフロ-リングの色に合わせています。
玄関タイルはOさんのアイデアで、5種類のタイルを張り分けています。


螺旋階段も形になりました。段板は床のフロ-リングの色に合わせてこげ茶色です。
手摺は複雑な形なので鉄パイプで造りました。現場で調整しながらの設置です。トラックに溶接機も乗っています。


予備室として使えるロフトもいい感じで出来ました。
2階、子供用ベッドの壁はOさん自ら左官仕事をしました。左官屋さんに材料をこねてもらい、ゼブラ柄に仕上げました。お気に入りのコ-ナ-になるでしょう。思い出いっぱいですね!


3階居間の扉がつきました。扉の上が丸くなっています。木の板が貼ってあるようにみえますが、コストダウンの工夫をしています。見た目よりもリ-ズナブルにできました。これもこげ茶色になります。
扉の戸当りも付きました。いつもと同じ、積み木ブロック風です。
16.検査・引き渡し


建物が完成すると検査機関による工事完了検査があります。無事合格し、5月中旬に建て主さんによる検査・引渡しが行われました。
工事の途中で何度も見ていただいているので大きな是正工事はありません。今回は塗装が若干遅れたので残工事として説明し、いつまでに完了させるかを確認していただきました。
引渡しの際に記念撮影をしました。これからもメンテナンスを通してお付き合いします。よろしくお願いします。
 完成写真はこちらから。
完成写真はこちらから。
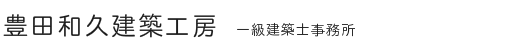
 HOME
HOME